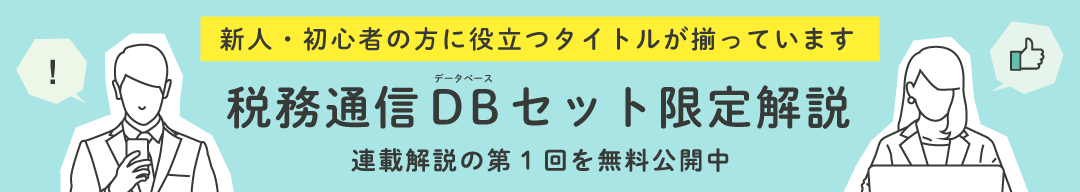[全文公開] 基礎からわかる資産税(相続税、贈与税、財産評価、譲渡税) 第1回 相続税、贈与税の基礎知識(その1)【税務通信データベース セット限定解説】
アタックス税理士法人 村井克行
|
【略歴】
アタックスグループ パートナー、アタックス税理士法人 代表社員税理士 組織再編や相続対策など最新の税法・会社法の知識を生かし、主にオーナー企業向けの総合的な支援業務に従事。 (2022年4月現在)
|
税理士事務所の若手や新人職員の方、これから資産税業務に取り組もうとされている税理士の先生方を対象に、相続税、贈与税、財産評価や譲渡税という資産税全般についてわかりやすく解説をしていきます。
第1回は相続税、贈与税の基礎知識につきまして2回に分けて解説いたします。
1.相続税とは
(1)相続税
亡くなった方(被相続人と言います。)の財産を「相続」などで取得した方(相続人等と言います。)を対象として、取得した財産の評価額に基づき課される税金です。
(2)相続税を課される人
①相続開始による財産の取得者
「相続」で財産を取得した相続人の他、遺言により「遺贈」で財産を取得した方や死亡を原因とする「死因贈与」で財産を取得した方も対象です。
②相続時精算課税制度の適用者等
この他にも、例えば次のような方も対象となります。
イ) 生前に贈与を受けた方で「相続時精算課税制度」の適用を受けた方
ロ) 自社株について「贈与税の納税猶予」の適用を受けていた方
ハ) 後述の「みなし相続財産」を取得した方 など
なお、「相続」などで財産を取得した相続人等のうち、相続開始前3年以内に「暦年課税制度」で生前に贈与を受けた方は、この贈与についても相続税の対象となります。
③人格のない社団等
また、相続税は基本的に個人に対して課される税金ですが、「人格のない社団または財団」や「持分の定めのない法人」に対して相続税が課される場合もあります。
イ) 「人格のない社団または財団」
ある目的のために集まった個人の集合体(社団)や財産の集合体(財団)で、法人化されていないもの。PTAやマンション管理組合などが該当します。
ロ) 「持分の定めのない法人」
学校法人や宗教法人、一般社団法人や一般財団法人などが該当します。なお、相続税が課せられるのは、次の場合に限られます。
a. 遺言によるこれら法人への寄附によって相続税の負担が不当に減少する結果となる場合
b. 同族理事の割合が2分の1を超えるなど、特定の一般社団法人・一般財団法人に該当する場合
(3)相続税の対象となる財産
① 本来の財産とみなし相続財産
本来の財産とは、土地、借地権や家屋、現預金、株式、書画骨董、貴金属、貸付債権など被相続人の財産で、相続人等が相続などで取得するものです。
なお、家族名義の預金や被相続人名義に変更登記されていない不動産、未登記の建物であっても、実質的に被相続人のものである場合には、被相続人の相続財産に含まれます。
また、例えば、死亡により給付を受ける生命保険金や死亡退職金は被相続人から相続などで取得した財産ではありませんが、相続などで取得したものとみなして(みなし相続財産と言います。)相続税の対象となります。
② 無制限納税義務者と制限納税義務者
相続人等のうち、国内に住所がある場合、国内に住所がないけれども日本国籍があり10年以内に国内に住所があった場合などは、無制限納税義務者として取得した財産の全てについて相続税が課されます。
無制限納税義務者に該当しない制限納税義務者は、取得した財産のうち国内にあるものに対してのみ相続税が課されることになります。
したがいまして、無制限納税義務者、制限納税義務者のいずれに該当するのか、その財産は国内にあるものとなるのか、という判断はとても重要になります。
③ 非課税財産
例えば、生命保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人(相続放棄などにより実際には財産を相続しない方も含めた概念です。)の数」までの金額、お墓、相続税の申告期限までに国などに寄附した財産は、公益性や政策的見地、国民感情の点から、相続税の非課税財産として相続税の対象から除かれています。
なお、香典は被相続人のものではないため、相続税の対象にはなりません。
(4)財産の評価
相続税の計算をする際の財産の評価額は、特別の定めがあるものを除き、相続などで財産を取得したときを課税時期として、そのときの「時価」によるものとされていますが、実務的には「財産評価基本通達」に基づいて評価することになります。
なお、通達どおりに評価していたとしても、その評価が行き過ぎた節税策の結果であるなど、実態にそぐわない場合には次の取扱いがありますので、十分な注意が必要です。
|
財産評価基本通達 第6項 (この通達の定めにより難い場合の評価) 6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。 |
2.贈与税とは
(1)贈与税
財産を「贈与」で取得した方を対象として、取得した財産の評価額に基づき課される税金です。
① 相続税の補完税
生前に贈与で財産を移動することで安易に相続税をゼロまたは軽減することができないよう、生前の贈与に対して贈与税を課しています。
このため、贈与税は相続税の補完税と言われています。
② 死因贈与
先述のとおり、「死因贈与」で財産を取得した方は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
③ 対象者の範囲
次の方も対象となります。
イ) 不動産や株式などの名義変更を行ったが適正な対価の支払いがない場合の、名義変更を受けた方
ロ) 後述の「みなし贈与財産」を取得した方
④ 人格のない社団等
また、先述の相続税と同様、贈与税は基本的に個人に対して課される税金ですが、「人格のない社団または財団」や「持分の定めのない法人」に対して贈与税が課される場合もあります。
(2)贈与税の課税方法
① 暦年課税制度
1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に対して累進税率を適用して贈与税を計算します。
② 相続時精算課税制度
60歳以上の直系尊属である父母、祖父母から18歳(2022年3月までは20歳)以上の直系卑属である子、孫への贈与について選択により適用することができます。
1年間に贈与で取得した財産の合計額から特別控除額を差し引き、その残額に対して一律20%の税率を適用して贈与税を計算します。この特別控除額は2,500万円を限度とし、前年以前に既に控除している場合は、その残額が限度額となります。
なお、この相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者(財産をあげた方です。)からの贈与については暦年課税制度を適用することはできなくなります。
③ 相続が発生した場合
贈与者に相続が発生した場合、相続開始前3年以内の「暦年課税制度」による贈与、「相続時精算課税制度」による贈与について、先述のとおり相続税の対象となります。この際、贈与時点での評価額が適用され、支払った贈与税については贈与税額控除が適用されます。
(3)贈与税の対象となる財産
① 本来の財産とみなし贈与財産
先述の相続税と同様、例えば次のような場合には、みなし贈与財産として贈与税の対象となります。
イ) 被相続人や自身以外が保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合
ロ) 個人から著しく低い価額で財産を購入した場合
ハ) 個人から債務免除を受けた場合
② 無制限納税義務者と制限納税義務者
先述の相続税における取扱いを参照してください。
③ 非課税財産
先述の相続税と同様、例えば、扶養義務者からの通常の生活費や教育費、「住宅取得資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」贈与のうち一定の金額、通常のお祝い金や贈答品などは、公益性や政策的見地、国民感情の点から、贈与税の非課税財産として贈与税の対象から除かれています。
なお、法人からの贈与は贈与税の対象ではないため贈与税は課されませんが、所得税の対象となります。
(4)財産の評価
先述の相続税における取扱いを参照してください。
3.民法の基礎知識
相続税の計算に必要となる「相続人」と「法定相続分」を解説します。
(1)相続人
① 相続人の範囲
相続人となり得るのは、次の方です。

イ) 配偶者
ロ) 子(子が相続開始以前に死亡している場合などは代襲者として、その子や孫)
ハ) 父母、祖父母などの直系尊属
ニ) 兄弟姉妹(またはその代襲者として、その子)
② 相続人の順位
実際には次の順序で相続人となります。
イ) 第一順位:配偶者と子(またはその代襲者)
ロ) 第二順位:子やその代襲者がいない場合、配偶者と直系尊属
ハ) 第三順位:直系尊属もいない場合、配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲者)
なお、配偶者がいない場合には、それぞれ、子(またはその代襲者)、直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲者)のみとなります。
(2)法定相続分
民法で定められた相続財産に対する取り分です。
① 相続人が「第一順位:配偶者と子」の場合
イ) 配偶者1/2、子1/2
ロ) 子が複数の場合は、子の法定相続分を均等に分けます。
② 相続人が「第二順位:配偶者と直系尊属」の場合
イ) 配偶者2/3、直系尊属1/3
ロ) 直系尊属が複数の場合は、直系尊属の法定相続分を均等に分けます。
③ 相続人が「第三順位:配偶者と兄弟姉妹」の場合
イ) 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
ロ) 兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の法定相続分を均等に分けますが、父母の片方が同じである半血兄弟姉妹については、父母の両方が同じである全血兄弟姉妹の1/2として計算します。
なお、配偶者がいない場合には、それぞれ、子(またはその代襲者)、直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲者)の法定相続分は1となります。例えば、子が2人で配偶者がいない場合、子の法定相続分は1となり、子1人についてそれぞれ1/2となります。
本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします