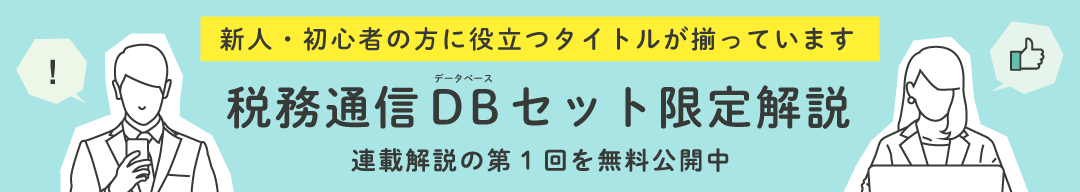[全文公開] 国税調査査察官歴38年の税理士が解説!税務調査の心構え 第1回 税務調査とは何か【税務通信データベース セット限定解説】
税理士 吉田 憲司
|
【略歴】
東京国税局査察部統括査察官、東京国税局統括国税実査官、東京国税局調査部統括調査官、東京国税局資料調査課課長、玉川税務署長、杉並税務署長などを経て現在税理士 (2024年4月現在)
|
はじめに
新しく経理部門に配属された方を対象に、実際の税務調査の現場で起こっていること、議論されていることを中心に解説します。税務署側と納税者側との両方の目線でポイントを絞って説明していきます。調査事例はできる限り実例に即して、法令解釈よりも、調査現場で起こる事象をピックアップして解説します。税務調査に対する正しい知識と心構え、対応姿勢を身に着け、調査官の次の一手を読み解きましょう。
〇税務調査に関する基本的な知識
(1)会社を取り巻く税金の種類
会社が納める税金には、さまざまな種類があります。主なものは次のとおりです。
| ① 法人税 | 会社の所得に対して課される国税です。税率は一律23.2%ですが、中小法人の場合は一部15%(又は19%)になります。 |
| ② 地方法人税 | 法人税の一部を地方財源として都道府県に配分するための税金で、法人税額に対して課される国税です。税率は10.3%です。 |
| ③ 法人住民税 | 会社の事業所がある都道府県と市区町村に納める地方税です。税率は自治体によって異なります。 |
| ④ 法人事業税 | 会社が利用する公共サービスや施設の費用を一部負担するための都道府県に納める地方税です。税率は会社の種類や所得によって異なります。 |
| ⑤ 消費税 | 物やサービスの消費に課される国税です。課税売上が一定額を超える場合に納税義務が発生します。税率は10%(軽減税率は8%)です。 |
| ⑥ 源泉所得税 | 給料や報酬などを支払う際、一定額の税金を天引きし、役員や従業員に代わって納税する国税です。原則、給料日の翌月10日が納付期限です。 |
(2)税務調査とは
税務調査とは、法人や個人が行う税務申告に対して、税務署が、申告内容が正しいかどうかを確認することです。
法人税や所得税をはじめとする、我が国の税金の多くは、法人や個人の納税者が自ら税額を計算して申告・納付する申告納税制度が採用されています。申告も納税も「自己申告制」であるため、税額の計算ミスや虚偽の申告が起きる可能性もあり、不正行為の防止や申告内容の確認を目的として税務調査が行われています。調査方法には、机上調査と実地調査とがあります。
机上調査は、文字通り、調査官が税務署内の自分の席上で会社の申告書をチェックし、申告書に誤りや税務署保有資料との不一致があった場合に、電話や文書で質問したり、説明資料の提出を求めたりするものです。
実地調査は、税務署が机上調査では確認できない、あるいは大きな問題点や不正経理等が見込まれると判断した場合に行います。調査では、税務署の調査官が、会社の事務所や工場にて数日間、社長や役員らへの質問や、会社の帳簿・領収書などの検査を行ったり、資料の提出を求めたりして進められます。
実地調査した結果、申告内容に問題がなければ、後日「申告是認通知書」という文書が会社に送付されますが、申告内容に不審点があれば、調査官がさらに数日会社に来たり、取引先に行ったりした上で、誤りなどが発見された場合には、最後に申告の修正と追加納税を求められることになります。
また、実地調査には強制調査と任意調査の2種類があります。強制調査は脱税の疑いがある場合に、事前の通知なく、裁判所の令状を持って行われる調査(いわゆる「マルサ」)です。一方、任意調査は一般的な調査で、原則、事前に通知があります。
全国には約5万6,000人の税務職員がおり、その多くが税務調査に従事しています。税務署では調査官に「真実に迫れ!」と教えています。調査官が、真実の取引を各自の五感で察知し、つかんだ証拠と会社の帳簿記録とを比較検討すること。それが税務調査であると、税務署では教えられています。
昨今、調査対象となる個人・法人の納税者の急激な増加や、経済活動のグローバル化、高度情報化、複雑化、税務訴訟への対応の必要性の高まり、さらには新しい取引形態の出現もあって、税務調査には多くの日数を要することとなっています。このため、調査件数は減っており、税務調査を受ける確率は年々低くなっています。しかし、いつ税務調査があっても慌てないように、税務調査に対して正しい理解と準備をしておくことが大切です。
(3)誰が税務調査の対象になるのか
税務調査は、法人や個人事業主だけでなく、サラリーマンやフリーランスなどに対しても行われることがあります。税務調査の対象になりやすい個人の特徴としては、次のようなケースが挙げられます。
|
・遺産を相続したことがある ・ネットオークションなどによる副収入がある ・仮想通貨取引で利益が出ている ・未成年や学生でもアルバイトや株の取引などで一定の所得がある ・資金援助を受けた、高額なプレゼントをもらった など |
税務署はこれらのケースについて、相続税や贈与税、所得税などの申告漏れがないか目を光らせつつ、新聞・雑誌・テレビ番組・YouTubeからも情報を収集しています。
また、法人や個人事業主の利益に大きな変動があったり、同業他社と比べて利益率が低かったりする場合や、消費税の還付があったり、少額の赤字が続いたりする場合などは、調査対象に選ばれやすくなります。
AIを駆使して申告事績と資料情報の突合せを自動的に行い、問題ある申告を選び出すなど、税務署の選定技術はここ数年で飛躍的に向上しています。問題があってもなくても、3年~5年ごとに定期的に行う実地調査やその対象法人を「周期該当(法人)」と言っていましたが、いまや死語になりつつあるようです。
(4)調査を受ける確率は何パーセント?
どの会社にも必ず税務調査が行われるという訳ではありません。3年ごとに調査を受けている会社もあれば、一度も税務調査を受けたことがない会社もあります。日本を代表する超大企業には毎年のように調査が入っています。
全国には約328万社の法人があり、令和3年度には約4万1,000社が調査を受けています。単純計算で1.25%の確率、約125年に一度ということになります。税務調査は、税務署が納税者の申告内容に不正や誤りがないかを確認するために行うので、どの会社でも、誰にでも起こりうることですが、確率はそう高くありません。
税務調査を受ける割合を「実調率」と言って、税金に関する公平性を議論する際の指標とされ、これまで国税庁が公表してきました。税務署ではできるだけ多くの職員と時間とを調査事務に振り分けていますが、コロナ禍もあり、実地調査件数は令和2年度には過去最低に落ち込んでいます。
この他にも、納税者の税に対する不公平感を表す言葉として、「クロヨン(9:6:4)」とか「トー・ゴー・サン・ピン(10:5:3:1)」という言葉もありましたが、最近あまり耳にすることはなくなりました。
時々来るから、忘れたころに来るから、突然来るから、「税務調査は怖い」と言われるのでしょうか? 税務調査は決して怖いものではありませんが、事前に備えておくことが大切です。正しい知識と準備を持って、税務調査に臨みましょう。
|
「クロヨン」「トー・ゴー・サン・ピン」とは? |
|
「クロヨン」「トー・ゴー・サン・ピン」とは、税務署が把握している所得には業種によって大きな差があり不公平であることを表す言葉です。実際の所得を「10」とすると、そのうち税務署が把握している割合は、 ・給与明細があり、毎月の給料が銀行振込み中心のサラリーマン:9割(10割) ・現金取引があり、確定申告により所得を自己申告する自営業者:6割(5割) ・生産量や収穫量、自家消費量がつかみにくい農業や水産業者:4割(3割) ・政治家:(1割) であるとされ、把握されている所得が少なければ納める税金も少なく、不公平であるというものです。これらの割合が正しいかどうかは定かではありませんが、制度の違いなどから、所得の捕捉率に差があった(今でもある)ことは否めません。 |
(5)プロの味付け~尊敬の的と畏怖の的~
納税者にとって税務調査を受けることは、仮に自分が不正をしていなくても、「嫌なもの」「恐ろしいもの」だとよく言われます。これは、「調査される」ということに伴う特有の心理や「税務調査」に対するイメージによるほか、税務調査の性格上、個人が秘密にしておきたい、身内にすら明かしたくないような財産関係などにも否が応でも立ち入ってくることに原因があるものと思われます。
加えて、税務調査を受けたことも、受けていることも、その内容や結果なども、確定申告前の一時期に数件報道されるくらいで、巷の人には知らされていないことが、「怖い」というイメージを作り上げているのかもしれません。
だからと言って、「税務調査はやめるべきだ」という声は聞かれませんし、それどころか、「国税は調査すべきだ!」と連日報道されている分野もあるようです。
適正な申告をしている納税者からすれば、税務調査を受けることは全く心外なことかもしれません。税務署としても調査技術の向上に努めて、できるだけ効率的に調査を行い、早期に適正か否かの判断を下すように配慮する必要があります。
一方で、不誠実な申告者にとっては、税務調査は恐ろしいものでなければなりません。脱税などの不正の事実を安易に見逃してしまうような税務調査では、税金での争訟事件こそ少なくなるかもしれませんが、結局において、誠実な納税者との課税の公平性を欠くことになり、ひいては国の財政基盤を危うくすることになりかねないと言っても過言ではありません。
少しハードルは高いですが、適正な申告をしている「優良申告法人」には、税務署長が直々に会社を表敬訪問し、適正申告を称えるということも行っています。
「正直者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」という言葉を知らない税務職員はいません。この言葉は、アメリカの税務専門家で、GHQ内国歳入課長であったハロルド・モス氏が、昭和24年の国税庁創立時に職員に対して贈ったものです。モス氏は、戦後の日本の税制改革に大きな影響を与えた人物で、マッカーサーの要請で来日し、国税庁の創設や「シャウプ勧告」で有名なシャウプ博士の招聘に携わりました。
国税庁の目標として、善良な納税者には信頼され、悪質な納税者には恐れられるような存在であれという意味が込められています。
本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします






 AIによる要約文を取得しています...
AIによる要約文を取得しています...