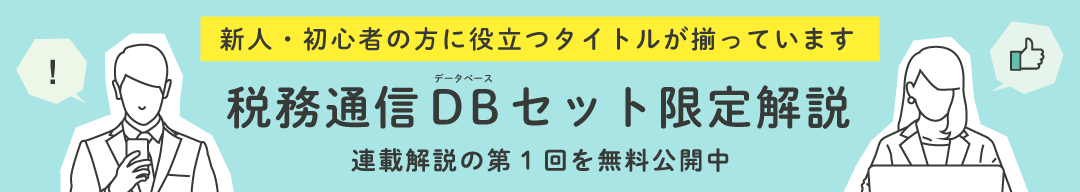税務通信ビギナーのための「税務通信」掲載資料の使い方 第1回 業種別・資本金階級別にみる役員賞与・役員給与の額一覧

この解説では、週刊「税務通信」に掲載している資料について、「税務通信」初心者の方向けに「何のための資料なの?」「どうやって使うの?」といった疑問に答えつつ、使い方をご説明いたします。
今回は、 №3804 (令和6年6月3日号)に掲載の「決定版 業種別・資本金階級別にみる役員賞与・役員給与の額一覧」を取り上げます。

 Q1
:何のための資料ですか?
Q1
:何のための資料ですか?
 A
:同業他社における役員給与や役員賞与の支給額の傾向を確認するための資料です。
A
:同業他社における役員給与や役員賞与の支給額の傾向を確認するための資料です。
内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額(過大役員給与)は、損金の額に算入できません( 法法34 ②)。
過大であるか否かの判断は難しいところですが、以下のような事情を勘案したうえで、その役員の職務の対価として相当であると認められる金額を超える部分は、過大と判定されるおそれがあります( 法令70 一イ)。
① その役員の職務の内容
② その内国法人の収益
③ その使用人に対する給与の支給の状況
④ その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況 等
①~③については自社に関する内容ですが、④については同業他社に関する情報が必要となります。しかし、比較対象とする類似法人の具体的な抽出方法や支給状況の比較方法についての法令の定めはありません。また、一般的に、普通の会社が他社の給与の支給状況を把握することは容易とはいえません。
そこで、今回掲げた資料では、業種や資本金階級の区分別に、法人の役員給与と役員賞与の支給額に関する情報をお届けしています。
なお、沖縄の酒造メーカーについて過大役員給与を巡り争われた裁判例(東京地裁・平成28年4月22日判決)では、企業側が「類似法人の役員給与の支給状況等を把握することは不可能である」と主張したのに対し、国側は、財務省や国税庁が公表している「法人企業年報特集」や「民間給与実態統計調査」及び税務関係の雑誌(税務通信)の記事や書籍等の資料から、類似法人の一人あたりの平均役員給与を算定することも可能であると反論しています(本誌 №3413・6頁 、 №3433・53頁 等)。
 Q2
:元のデータはどこから来ていますか?
Q2
:元のデータはどこから来ていますか?
 A
:財務省・財務総合政策研究所の公表資料「法人企業統計年報」を基にしています。
A
:財務省・財務総合政策研究所の公表資料「法人企業統計年報」を基にしています。
https://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g859/859.html
法人企業統計調査は、わが国における営利法人等の企業活動の実態を把握するため、標本調査として実施されている統計法に基づく基幹統計調査です。この調査資料から、役員給与・役員賞与に関する部分を抽出してまとめたものになります。
基幹統計調査については、年に数回、週刊「税務通信」誌面に調査実施のお知らせを掲載しています。最近では、下記のとおり №3799(令和6年4月22日号)・50頁 に掲載しました。

 Q3
:この資料を、どのように使ったらよいのでしょうか?
Q3
:この資料を、どのように使ったらよいのでしょうか?
 A
:類似法人における支給状況の傾向の確認や、自社の役員給与等の支給額を決定する際の参考としてご利用できます。
A
:類似法人における支給状況の傾向の確認や、自社の役員給与等の支給額を決定する際の参考としてご利用できます。
(使い方の例)
 当社は卸売業と小売業を営む、資本金8,000万円の会社です。資料のどこを見ればよいでしょうか?
当社は卸売業と小売業を営む、資本金8,000万円の会社です。資料のどこを見ればよいでしょうか?

 業種は「卸売業、小売業」で資本金「5,000万円~1億円未満」の箇所を参照してください。
業種は「卸売業、小売業」で資本金「5,000万円~1億円未満」の箇所を参照してください。
 これを見ると、平均役員賞与は約156万円、平均役員給与は約973万円ということですね。これは年額ですか?
これを見ると、平均役員賞与は約156万円、平均役員給与は約973万円ということですね。これは年額ですか?
 そうです。令和4年度調査(令和4年4月1日~令和5年3月31日に決算期の到来した標本法人)のデータになります。
そうです。令和4年度調査(令和4年4月1日~令和5年3月31日に決算期の到来した標本法人)のデータになります。
 そうすると、賞与が年2回として1回あたり約78万円、給与が年12回として1回あたり約81万円ですか。この金額を超えたら過大になってマズイということですか?
そうすると、賞与が年2回として1回あたり約78万円、給与が年12回として1回あたり約81万円ですか。この金額を超えたら過大になってマズイということですか?
 この数値はあくまでも業種別の平均値ですので、参考とお考えください。役員給与が過大かどうかは、
Q1
のとおり、このほかに「①その役員の職務の内容、②その内国法人の収益、③その使用人に対する給与の支給の状況」等を総合的に勘案して判断されます。
この数値はあくまでも業種別の平均値ですので、参考とお考えください。役員給与が過大かどうかは、
Q1
のとおり、このほかに「①その役員の職務の内容、②その内国法人の収益、③その使用人に対する給与の支給の状況」等を総合的に勘案して判断されます。
本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします