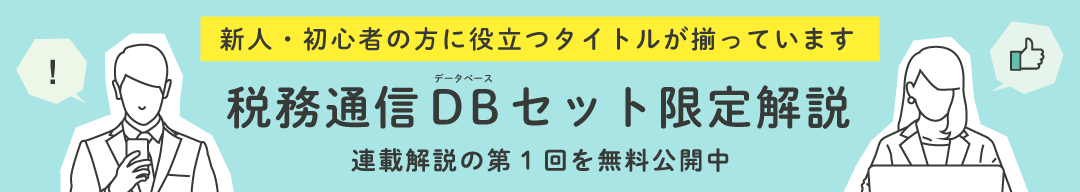実務で使える!はじめてのキャッシュフロー 第1回 キャッシュフローの重要性と資金繰りを良くする・悪くする原因
税理士 松田 修
|
【略歴】
税理士 松田 修 昭和61年税理士試験合格。村田簿記学校講師(法人税法、簿記論担当)を経て、辻会計事務所(現 辻本郷税理士法人)入所。数多くの企業の会計・税務業務や経営相談などを経験し、現在は税理士松田会計事務所所長
(2024年6月現在)
|
はじめに
最近は「キャッシュフロー重視」「キャッシュフロー経営」という言葉が定着していますが、これは西暦2000年に上場会社に「キャッシュフロー計算書」の作成・公開が義務付けられたのが始まりです。
非上場会社には「キャッシュフロー計算書」の作成・公開は義務付けられていませんが「キャッシュフロー」は日本語では「資金繰り」になりますので、すべての会社に重要なテーマになります。
本連載では、この「キャッシュフロー」「資金繰り」に焦点をあて、様々な角度からキャッシュフロー(資金繰り)改善の方法などを解説していきます。
1.資金繰り、キャッシュフローの重要性
会社にとっても、社長にとっても、従業員にとっても、最も不幸なことは会社が倒産することです。その会社で働く従業員の家族も、仕入れ先などの取引先も同時に不幸に見舞われます。
会社の「倒産」とは、会社に現金預金(キャッシュ)がなくなることです。社長など経営陣の最大の望みは倒産の心配なく会社が順調に発展していくことではないでしょうか。
社長や経営陣の方に「経営上の一番の心配は何ですか?」と質問しますと、返ってくる答えで一番多いものは「会社の現金預金(キャッシュ)がなくなること」、又は「現金預金(キャッシュ)が少なくなること」です。
そうです、会社にとって一番の悩みはお金の悩み、資金繰りの悩みなのです。
私も会社を経営していますが、確かに会社の現金預金(キャッシュ)が少なくなった時が一番不安になります。私は税理士であり、会計の専門家なので、簿記会計も決算書も一般の方よりも知識が豊富ですが、それでも経営で一番大切なのは現金預金(キャッシュ)だと思います。会社の預金通帳のお金が十分にある時は自信を持って経営に専念できますが、預金通帳の残高が少なくなると、とたんに恐怖に襲われます。
次に、現金預金(キャッシュ)が多い会社のメリット、現金預金(キャッシュ)が少ない会社のデメリットをみてみましょう。
〇現金預金(キャッシュ)が多い会社のメリット
・社長、経営幹部、従業員が元気で安心して経営にあたれる
・現金預金(キャッシュ)に余裕があるので長期的視野で経営にあたれる
・売上を増やすための広告宣伝費などを使える
・必要な固定資産を購入又はリースすることができる
〇現金預金(キャッシュ)が少ない会社のデメリット
・常に倒産の恐怖に怯え、会社の雰囲気も暗くなる
・現金預金(キャッシュ)に余裕がなく長期的視野で経営にあたれないので、どうしても短期的、行き当たりばったりの経営になる
・てっとり早くお金がほしいので、過度の値引き販売を行う
・広告宣伝など販売促進にお金が使えないため新規のお客が増えない
・固定資産(店舗や備品)も古いままで、やがてお客も来なくなる
いかがですか?
やはり現金預金(キャッシュ)に余裕がないと、会社はどんどん活力がなくなってしまいますね。逆に現金預金(キャッシュ)に余裕がありますと長期的視野で経営できますので、この差は非常に大きなものになります。まして、この差が5年、10年続いたら......と想像するだけでも恐ろしくなります。
2.資金繰り(キャッシュフロー)を良くする、悪くする4つの原因
皆さんが社長など経営幹部から「半年先の資金繰りが厳しいから、現金預金を増やす方法、又は現金預金が減らない方法を考えてほしい」と言われたとします。
さて、現金預金を増やす方法、現金預金が減らない方法はいくつもありますが、皆さんはいくつ挙げられますか。
是非ここで続きを読むことを一旦中断して、その方法を紙に書いてみてください(実務上、可能かどうかは無視して、考えつく方法をできるだけ多く書いてください。)。
いかがですか。
皆さんは、いくつの方法を列挙できたでしょうか。
ここで皆さんが紙に書いたことをもう一度確認してください。どのような方法を考えたとしても、資金繰り(キャッシュフロー)を良くする原因は、下記のように4つに分類されます。
○現金預金が増加する仕組み
まず、現金預金が増加する仕組みを、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)を以下のように図形化して説明します(説明を単純にするために数字は簡略化してあります。)。

会社の現金預金が増加する原因は次の4つに分類されます。
① 現金預金以外の資産が減少する
② 負債が増える
③ 増資する(純資産が増加する)
④ 利益を出す(同じく純資産が増加する)
以下、一つずつ解説していきます。
①「現金預金以外」の資産を減らす
現金預金を増加させる原因の一つ目は「現金預金以外の資産の減少」になります。
下図の通り「現金預金以外の資産」が減少すると現金預金は増加します(すべて他の要素は変わらないと仮定して説明しています。)。

「現金預金以外の資産」が減少するとは、具体的には以下をいいます。
| ・売掛金、受取手形の回収 | ・受取手形の割引、裏書譲渡 |
| ・棚卸資産(商品・製品など)の減少(在庫の圧縮) | |
| ・有価証券、固定資産の売却 | ・貸付金、立替金、未収入金の回収 |
| ・保険積立金や敷金の解約 など | |
逆に、以下のように「現金預金以外の資産」が増加しますと現金預金は減少します。
| ・売掛金、受取手形の増加 | ・棚卸資産(商品・製品など)の増加(在庫が増える) |
| ・有価証券、固定資産の購入 | ・貸付金、立替金、未収入金の増加 |
| ・保険積立金や敷金などが増える など | |
②負債を増やす
現金預金を増加させる原因の二つ目は「負債の増加」になります。
下図の通り、負債が増えると現金預金は増加します。

負債が増加するとは、具体的には以下をいいます。
| ・新規の借入れ | ・社債の発行 | ・買掛金、未払金の増加 |
| ・支払手形の発行 | ・前受金の増加 など | |
逆に、以下のように負債が減少すると現金預金は減少します。
| ・借入金の返済 | ・社債の償還 | ・買掛金、未払金の支払 |
| ・支払手形の決済 | ・前受金の減少 など | |
負債は必ず後で返済、支払が来ますので、もちろんむやみに負債を増やすのは危険ですが、負債が増えると一時的には現金預金は増加します。
③増資する(純資産を増やす その1)
現金預金を増加させる原因の三つ目は「増資」になります。
下図の通り、増資を行うと「純資産」の「資本金」が増え現金預金が増加します。

逆に、株主に対する配当金の支払、自社株の取得、日本ではあまり行いませんが有償(払戻し)減資を実施しますと「純資産」が減少し、現金預金も減ります。
④利益を出す(純資産を増やす その2)
現金預金を増加させる原因の四つ目は「利益の計上」になります。
下図の通り、損益計算書(P/L)で利益が出ると「純資産」の「利益剰余金」が増え現金預金が増加します。

損益計算書(P/L)の「当期純利益」を増やす方法は、上記のように「収益を増やす」と「費用を減らす」の2つがあります。
〇収益を増やす
| ・売上を増加させる(売上数量を増加させる、単価を上げる) | |
| ・受取利息、受取配当金を増やす | ・為替差益を出す |
| ・給付金、助成金など雑収入を増やす など | |
〇費用を減らす
| ・売上原価、製造原価を減らす(コストダウン) |
| ・販売費及び一般管理費を減らす(経費の削減) |
| ・支払利息、割引料を減らす など |
上記とは逆に「当期純損失(赤字)」を出しますと、「純資産」の「利益剰余金」が減少し、現金預金も減ります。
3.なぜ資金繰り(キャッシュフロー)は4つに分類されるか?
簿記ではすべての勘定科目を次の5つに分類しています。貸借対照表(B/S)は「資産」と「負債」「純資産」グループ、損益計算書(P/L)は「収益」と「費用」グループに分類されます。
資金繰り(キャッシュフロー)を良くする4つの原因の「① 現金預金以外の資産を減らす」「② 負債を増やす」「③ 増資」は貸借対照表(B/S)の「資産」「負債」「純資産」の内容になります。
資金繰り(キャッシュフロー)を良くする4つの原因の「④ 利益を出す」の項目に入っているのは「収益」と「費用」グループになりますので、損益計算書(P/L)の内容になります。
以上の説明のように 簿記ではすべての勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つに分類されます。会社のお金の出入りを表しているのが簿記ですので、資金繰り(キャッシュフロー)を良くする原因は4つに集約することができるのです。

4.利益が出ても現金預金がないのはなぜか?
決算や月次で、社長に「今期(先月)は1,000万円の利益が出ました」と報告すると社長から「1,000万円の利益が出たというが、そんなにお金は残っていない。なぜですか?」と質問を受けることがあります。
理由はもうおわかりだと思いますが、資金繰り(キャッシュフロー)は解説しましたように「利益(損失)」を含めて4つの原因により決定されるからです(非上場の中小企業で増資や減資、株主配当金の支払がない場合には、それ以外の3つの原因で資金繰りが決定されます。)。
利益が出ても資金繰りが苦しいケースの一つ目は、「利益」以上に「現金預金以外の資産が増加」している場合です。
具体的には、得意先の倒産などにより回収できない不良売掛金が増大したケース、売れない商品など不良在庫が増大したケース、本社ビルや工場の建設、新規出店や設備投資などを利益以上に行っているケースが当たります。
利益が出ても資金繰りが苦しいケースの二つ目は、「利益」以上に「借入金の返済など負債が減少」している場合です。
以前、ある社長から「利益が出ているけれども資金繰りが苦しい。原因を調べてほしい」というご相談がありました。早速「決算書」を分析してみますと、「借入金」の返済が多すぎることが原因でした。
この社長は「借金」が嫌いで早く返済しようと「返済期間」を短く設定していました。会社の業績が良い時は利益も多く計上され、この計画でも借入金を返済することができましたが、会社の業績が落ち、以前ほど利益が上がらなくなってきますと、この返済計画では「利益」以上に借入金を返済しているため資金繰りが苦しくなっていました。
そこで、金融機関に相談して現在の「利益」でも借入金が返済できるような返済計画に見直してもらうようアドバイスしました(具体的には、返済期間を延ばしてもらうことになります。これを「リスケジュール」、略して「リスケ」と呼んでいます。)。
|
会社の現金預金が増加する原因は次の4つに分類される。 ① 現金預金以外の資産が減少する ② 負債が増える ③ 増資する(純資産が増加する) ④ 利益を出す(同じく純資産が増加する)
逆に会社の現金預金が減少する原因は次の4つに分類される。 イ 現金預金以外の資産が増加する ロ 負債が減る ハ 配当金の支払、自社株の取得(純資産が減少する) ニ 損失(赤字)を出す(同じく純資産が減少する) |
本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします