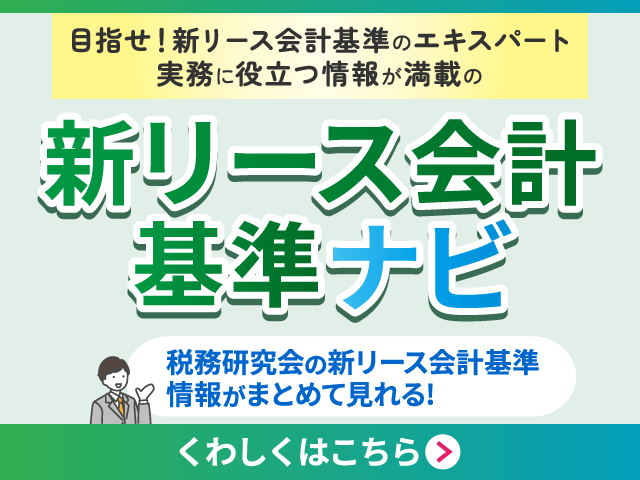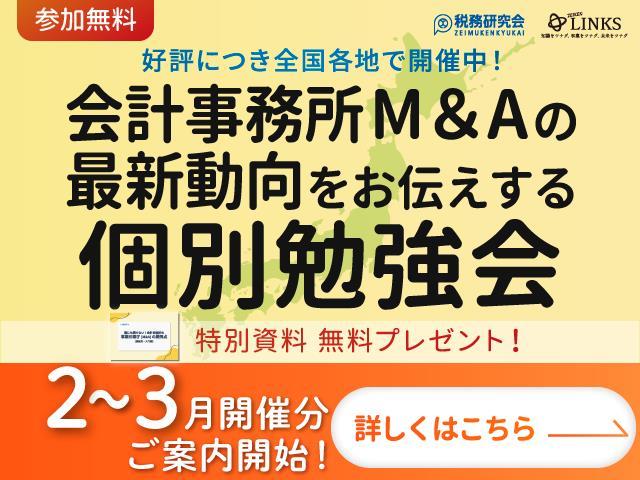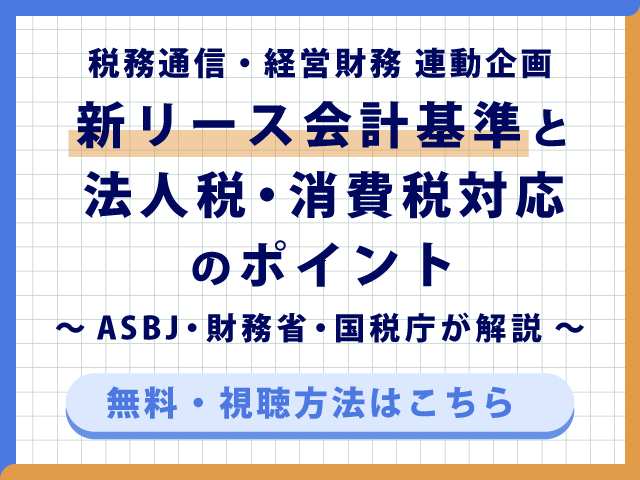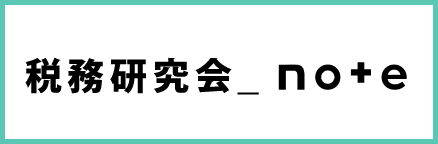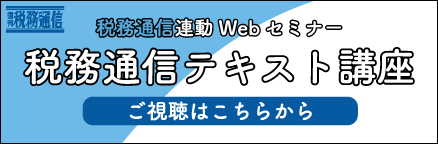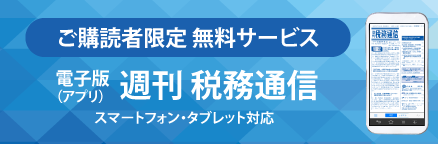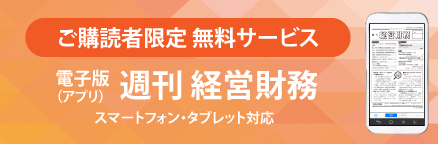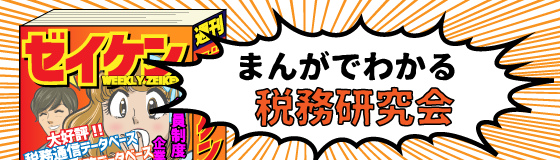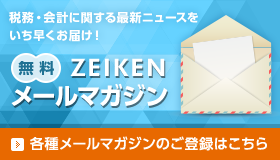プロフェッショナルによる税務通信のすゝめ~税務通信をあきらめない~【声でとどける税務通信 番外編】
2025/02/03 8:00
[税理士・村木 慎吾 氏]×[税理士・米津 良治 氏]両氏によるスペシャル対談を限定公開。税務通信との付き合いかた、普段の利用方法について、お二人のこれまでの経験則も含めて語っていただきました。
この対談が、税務通信をより有効活用したいあなたの、素晴らしいきっかけの ひとつとなりますように。
<パーソナリティ>

同志社大学卒業後、税理士法人ゆびすい、税理士法人トーマツを経て、平成21年、村木税理士事務所を開設。週刊税務通信 人気連載「実例から学ぶ 税務の核心」共同執筆者であるほか、著書多数。

上智大学卒業後、一般事業法人(経理部)、税理士法人勤務を経て、令和2年、BASE(べイス)総合会計事務所を開設。主な共著書に「会計事務所と会社の経理がクラウド会計を使いこなす本」(ダイヤモンド社)などがある。
お二人にとって、「週刊 税務通信」の位置づけは?
村木:私の中では個人でできる情報収集ツールのメインだと思っています。ヨイショするわけでも何でもなくて、私の経験上の話をすると、記事の内容を見ていても、やはり国税当局に取材されているものだなというのはわかりますし、ちゃんと確認を取っている内容だなと思われるので、そのような信頼性はあるなという。その分、堅苦しいことを書くことが多いですが、そういう意味では信頼性が一番あるのかなと私は思います。なので、私の中では情報収集していく中でのツールのまずはメインだと。当然、ほかにもメディアは、いろいろありますし、そこも、もちろん読んではいるんですけど、 メインツールとしては「税務通信」を使っているという感じですね。米津先生どうですか?
米津:私もそうですね、正確かつタイムリーな情報という位置づけで、税務通信さんは見ていますね。 他にもいろいろな情報源があって、それぞれの特徴がありますけど、何より正確でタイムリーな情報を見るんだったらここだなと思っています。
村木:私の周りもそんな感じなんで、意見が一致していてよかったです。
週刊 税務通信をどのように利用されていますか?
米津:環境の違いで利用方法がいろいろあると思いますが、村木先生はどういう風に使っていますか?
村木:若い頃のあまり知識がない頃と今では全然違うなというのはあって、昔は正直ほとんど読めなかったです。 書いている意味がわからなくて、ほとんど。 ただそこで先輩からのアドバイスもあって「諦めるな」と。なのでまずは分かる部分だけ読み続けましたね。とりあえず発刊されれば分かる部分だけ読んで、分からないものの中で興味があるものとか実務に関係している、自分のやっている仕事に関係しそうなものは先輩に聞いて教えてもらうというのを、若いうちはひたすら繰り返してました。で、 何年かしてくると分かる部分が増えてきたという感じの使い方で。その若いうちという意味でいくと、同じようなレベルの同僚と読み合わせしてましたね。
米津:読み合わせですか。
村木:私が先ほど言ったとおり、自分だけじゃどうしてもやめてしまうので、周りを巻き込んで同じレベルの人間を連れてきて「一緒に読もうよ」という話で読めば継続してできるので、その中で議論しながら教えてもらいながらというのをやっていましたね、昔は。で、今は紙で届いたら、全部、読んでます。 今は当然分からない部分ってそんなにないですけども、どっちかというと今は疑問が湧く。これを読んで、じゃあこの場合はどうだとか、この論点どうなんだとか、この考え方どうなんだという疑問をなるべく作るようにしてて、 例えば一冊に5つは疑問を出すという自分に課題を与えてて。
米津:すごいストイックですね。
村木:そうでしょ(笑) 疑問が湧いたら、それを相談できる仲間が今はいるので、どう思いますかって聞いたりしています。なので今は疑問を自ら作り、それを埋めることで勉強するというのをプラスアルファでしていますね。
米津:すごいですね。なかなかそこの領域までたどり着けるかというところもありますけど。でもやっぱり、最初は読んでいて何言ってるかわかんないというか、単語レベルでわからないワードが出てくるから読めないっていうのはある意味みんなそうなのかなというところで、 そこからこのわからないから見ないというサイクルに入っちゃわないようにした方がいいなと思いますよね。
村木:ちなみに米津先生どんな感じで使っていますか?
米津:私は少なくともいわゆる一面って言うんですかね、「展望」って書かれている「週刊 税務通信」の表紙のところに3つぐらいトピックがあって、かつ中身をかなりコンパクトに書いてもらっているところ。あそこは、最低限、目を通すようにしていて、そこから中の方の深掘りをしていくという見方で読んでいます。
村木:でもあれですね、私も若い頃に自分にアドバイスをするとしたら、その当時は誤解してたんですけど、「税務通信」を読んで記憶しないといけないと思ってたんですよね。
米津:あ〜、わかります。
村木:記憶は、私、苦手なんで、それをやろうとしたらしんどかったんですよね。だからやめちゃうっていうのもあると思うんですけど、若い自分に言えるとしたらそんな必要はない。とりあえず理解をしようと。細かい要件とか形式の話は、どうでもいいので、その内容の趣旨を軽く理解しよう、という感じで教えるような気がしますね。 趣旨を理解すれば、実務で同じ話であった時に、違和感のセンサーが働くんですよね。
米津:違和感、大事ですよね。
村木:だから何か趣旨と違うなと思えば、その時、調べればいいという流れにすればいいと思うので。今、聞かれている方で若い人いらっしゃったら、難しいでしょ? 難しいのは私も経験したんで、それはそうなんです。 ただ、ちょっと分かるとこだけ書いていることの趣旨を理解する癖をつけていけば、きっと役立つと思うので、それはぜひ自分が若い頃に教えてあげたかったなという気がしますね。
米津:そうですよね。お客さんと話をしていて、こういう風にすればいいんじゃないかみたいな話が出てきて、 いや、これなんかちょっとおかしい気がするなみたいな。そういう感覚を育むっていうのはとても大事なことですよね。
村木:そうですね。こんなんあったなと思えば、税務通信さんの検索ツールを使えばいいと思うので、記事検索すれば大体ヒットしますもんね。
オンライン版の「週刊 税務通信」=税務通信データベースはどのように使ってますか?
米津:とてもいいですよね。記事検索して見れるとか、あとはブックマークで保存もできるので、これは多分見るだろうなとか、これはお客さんに説明するときに、多分、見せながらやった方がいいよね、みたいなものがあるときには、ブックマークに取っておいたりしますね。
村木:しますよね。 あとネットという意味でいくと、「法令集」って非常にいいですよね。
米津:あれめちゃくちゃいいですよね、「法令集」は。動き早いし、括弧って辛いじゃないですか。括弧の中に括弧が・・・マトリョーシカみたいになっていたりするのが。
村木:(笑)
米津:あれを一気に消したりとか、 もしくは色をつけて何層目か分かるようになってたりとかっていう機能もあったりとか、印刷もしやすかったりとかベタ褒めになっちゃいますけど、今まで見てた条文検索の中で一番使いやすいなって思う。 やっぱり条文大事ですよね。
村木:ある程度まで来たらやっぱり条文読まないと結局分からないっていうところがあるので、逆に条文読めると圧倒的な武器になると思うんですよね。その読む際に、おっしゃったように、読みにくいので条文は。税務通信さんの法令集だと色分けしてもらってて、リンク貼ってるし非常に読みやすいので、これで慣れるっていうのは大事だと思いますね、非常に。
※ 声でとどける税務通信 特別企画「みんなの税務通信 第3回 税務通信をあきらめない」より、文章化するにあたり、編集部で一部修正
税務研究会では「週刊税務通信」読者様をサポートすべく
様々なスタイルのコンテンツをご用意しております!
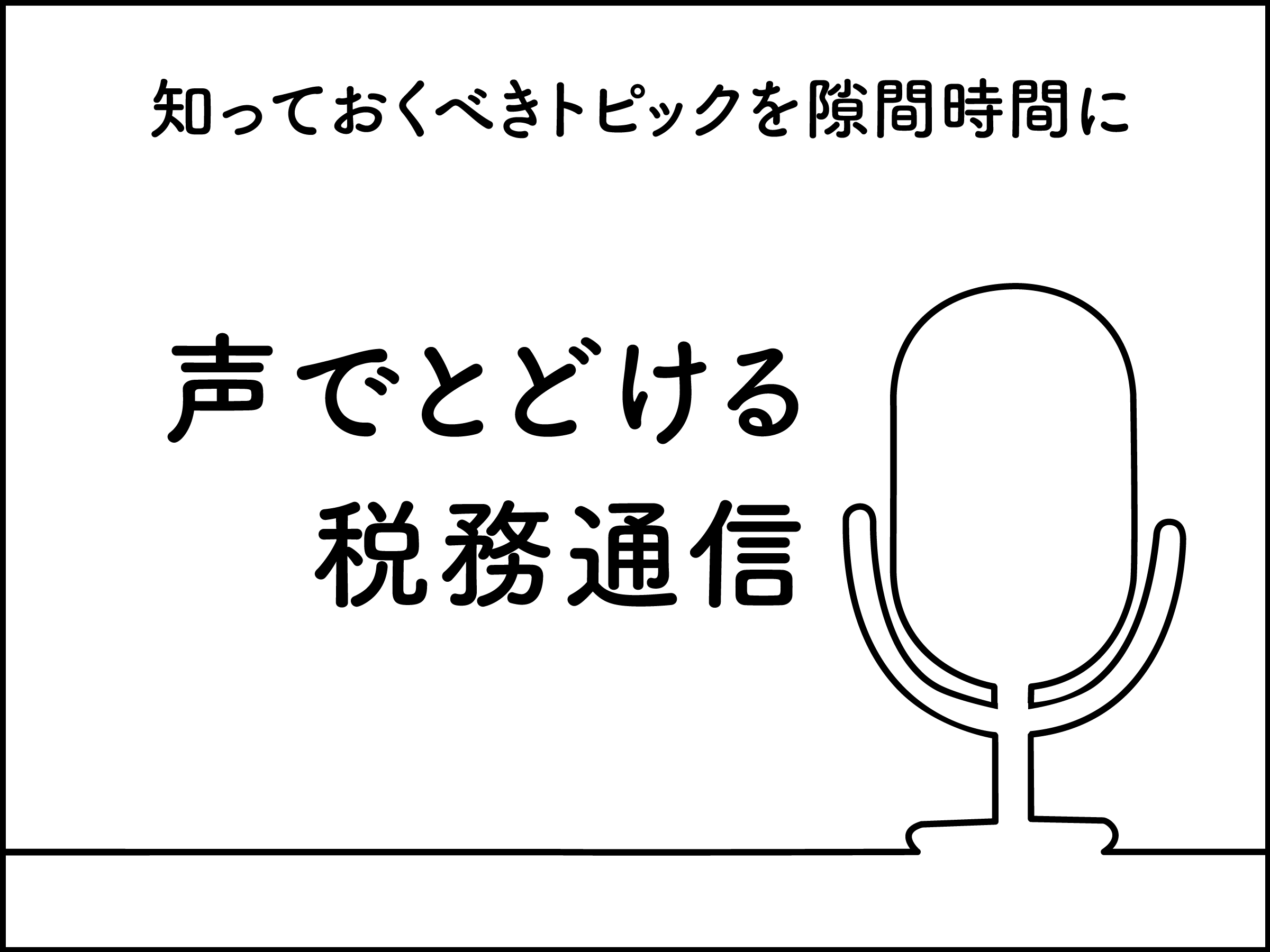
声でとどける税務通信
週刊税務通信の理解を深めるための実務情報を音声でお届けしています。
税理士、公認会計士、企業経理部で働く「あなた」のためのポッドキャストです。
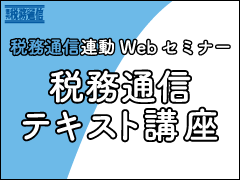
税務通信テキスト講座 <ご契約者様限定コンテンツ>
週刊税務通信を徹底活用していただく事をコンセプトに、本誌に掲載された旬な税務トピックスや実務上ぜひとも押えておきたい記事、人気コーナー「ショウ・ウィンドウ」などからピックアップして毎月Webセミナーを公開しています。
特定のテーマについて体系立てて学習するのではなく、記事内容を深く掘り下げてわかりやすく解説いたします。
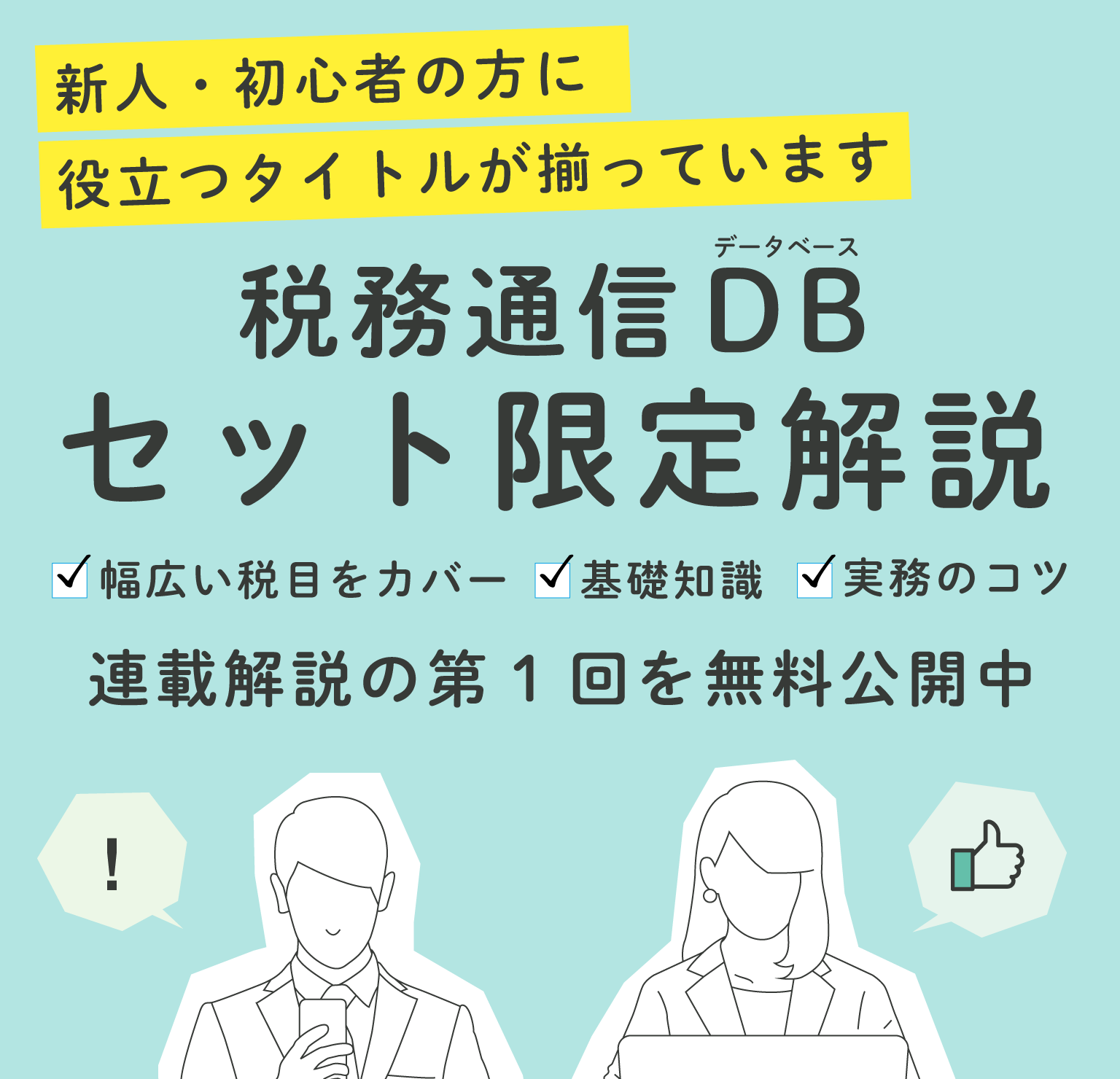
税務通信DBセット限定解説 <ご契約者様限定コンテンツ>
紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる解説記事です。
初心者向けの連載解説を主とし、幅広い税目をカバーしています。
税務通信データベース内で閲覧できます(紙版の週刊税務通信には掲載されません)。
最新号から約20年分のバックナンバーだけでなくご契約者様限定コンテンツまで
いますぐ閲覧できるIDをご案内します!
税務通信データベース
資料請求(2週間お試し はこちら)
※お試し終了後に自動で有料契約に切り替わることはございません