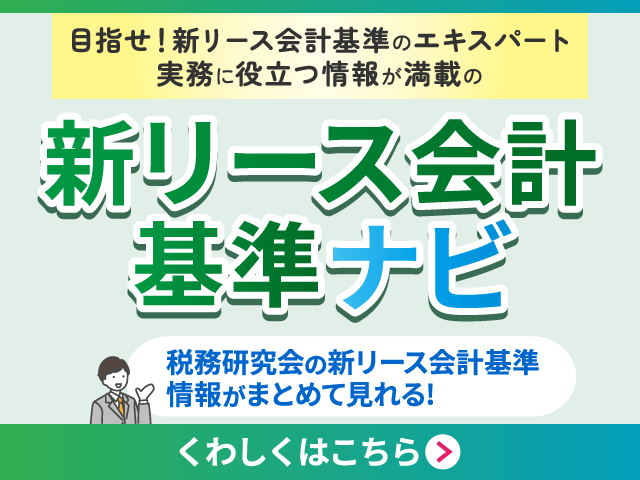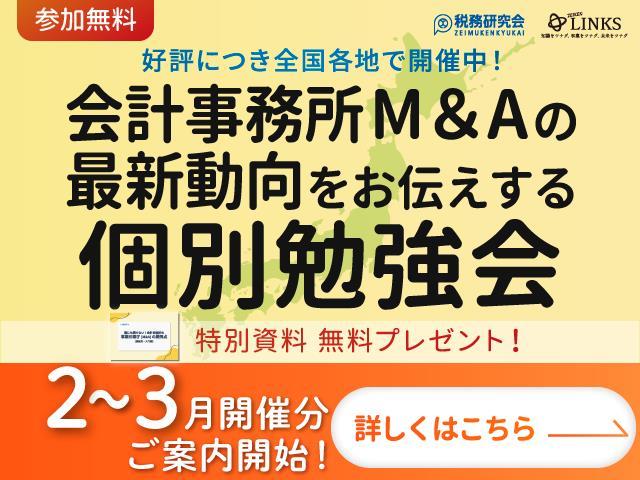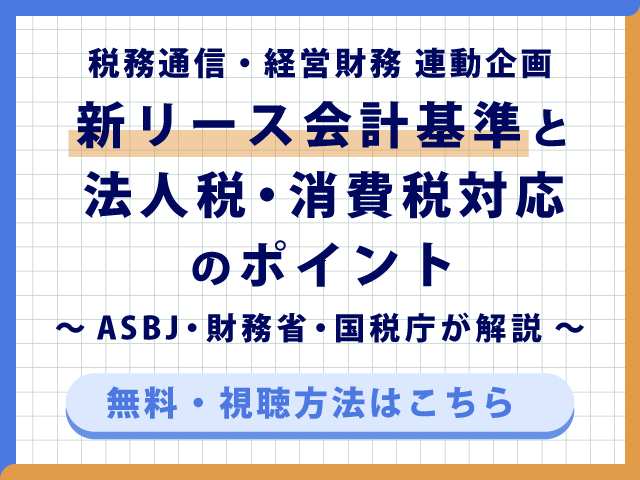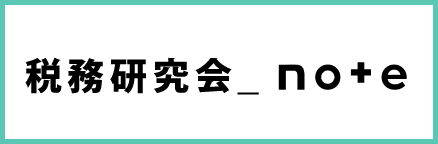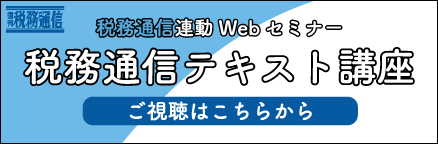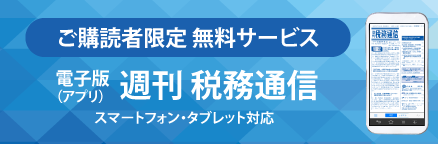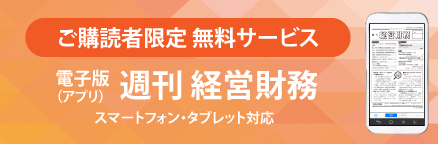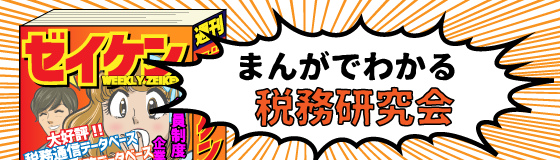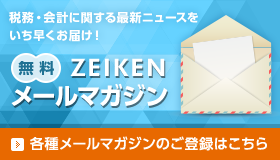インボイス導入がサラリーマンの経費精算や副業にも影響!?免税事業者への影響とは
2019/05/28 13:30
- インボイス
- 免税事業者
10月に予定通り消費税率が引き上げられると、同時にもう一つ、大きな消費税改正も行われることになります。4年後に予定されている「適格請求書等保存方式」・いわゆる「インボイス」制度の導入がそれです。
| インボイスとは 事業者の登録番号・取引内容・取引金額など一定の事項を記載した領収書等のことです。 課税事業者のうち登録を受けた事業者のみ発行ができ、免税事業者は発行できません。 |
インボイス導入後は、インボイスを発行できないこととなる消費税の免税事業者(おもに課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者や個人事業主など)が、取引から排除されてしまうのではないかといった懸念が強くささやかれています。こうした懸念が生まれるのはどうしてなのか?果たしてその心配は実現してしまうのか?今回はその辺りを探ってみたいと思います。
免税事業者との取引では仕入税額控除が受けられず、その分コストアップになってしまうのが最大の理由
インボイス導入で消費税の免税事業者が取引から排除されてしまうのではないかとの懸念が発生する理由は、ズバリ言って「取引先(仕入側)にとって仕入税額控除の対象にならなくなってしまうから」ということです。
| 仕入税額控除とは 事業者が国に納める消費税額を算出するにあたり、売上の消費税額から、仕入の消費税額を控除して計算する制度のことです。 消費税は、その名の通り"消費者が負担する税"であり、事業者は税金を負担する必要がありません。そのため、消費税を受け取った事業者は、受け取った消費税から仕入にかかった消費税をマイナスして納付できる仕組みとなっています。 |
これをわかりやすい例で説明しましょう。
あなたはとある企業の営業マンです。景気が回復しているとのことですが、インボイス導入後も企業の経費削減は続き仕事でタクシーを使うのも大変であることに変わりはないでしょう。しかし、約束の時間に遅れてはならじとタクシーに飛び乗ったとします。
2,000円のタクシー代を払って領収書をもらい、いつもどおり経理に提出したまではよかったのですが、ここで一言注意が来ます。
経理部員「この領収書は個人タクシーで"インボイス"になっていないんですよね。今度からは会社形式のタクシーを利用してくださいね。」
あなた 「どういうことですか?タクシーの料金は法律で一律に規制されているから、どこを使っても同じではないんですか??」
経理部員「料金は同じでも、インボイスの出る課税事業者のタクシーだと2,000円の10%が税額控除できて、会社の負担は実質1,800円で済むんですよ。だけど、あなたのもらってきた領収書は免税事業者の個人タクシーが発行したもので"インボイスではない"から、会社は丸々2,000円の費用を払わなければならないんです。同じサービスならコストの安いほうを選ぶのが会社の方針なのはご存じでしょう?」
あなた 「...以後気を付けます。」
インボイス導入は働き方改革にも大きく影響?
個人タクシーのすべてが免税事業者とは限りません。また、タクシー代も今のような一律制度が続くか断定はできませんが、インボイス実施に向けてはこうした話が山のように出てくるでしょう。インボイスが無ければ消費税の仕入税額控除ができませんが、それは間接的に企業のコストアップにつながってしまうわけです。
現在、「働き方改革」の名のもとに会社員の副業解禁なども本腰で検討されています。
日経新聞社の調査でも「大企業120社のうち約5割の企業が従業員に副業を認めている」とのことで、副業解禁の流れが一般企業に広がってきているようですが、これにもインボイスが影を落としかねません。
たとえば、今の話がタクシー代ではなく、会社の業務委託だったらどうでしょうか。同じ仕事を依頼するのでも、サラリーマンが副業として行う程度のものは売上高1,000万円に届くとは考えにくく、やはり仕入税額控除の対象にはならないでしょう。
これに対して、同じ内容の業務委託でも会社組織等でインボイスの発行できる課税事業者であれば、依頼主にとってはコスト的に有利になるケースが多くなるでしょう。
その挙句、副業の場合は単価の引き下げ要求が強くなったりすれば、何のための働き方改革だかわからなくなってしまいかねません。
6年間はある程度の控除を認める経過措置は設けられているが...
ただし、インボイス導入を巡ってこうした事態が問題になりかねないことは税務当局も十二分に理解しています。そこで、インボイス導入から3年間は、たとえインボイスの発行できない免税事業者との取引であっても80%分の仕入税額控除を認める等の経過措置が設けられています。
その内容は次のようなものです。
|
適格請求書等保存方式導入から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの 仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設 けられています(28年改正法附則52、53)。 経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
※国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式Q&A」問72より抜粋・一部編集(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf) |
このように経過措置はインボイス導入後6年にわたって続きますが、免税事業者と取引する立場にすれば仕入税額控除が本来より減少し、その分コストアップにつながることに変わりありません。
経費削減が叫ばれる中、企業はコストアップを受け入れてまで免税事業者との取引を続けるでしょうか...?
■ 関連記事
交際費5,000円基準にもインボイスが影響?インボイスと免税事業者の排除ケーススタディー2
■ インボイス関連書籍はこちら
■ 税務研究会が主催するインボイス関連セミナーはこちら