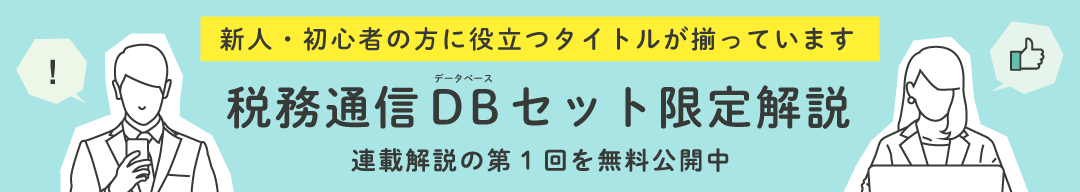続・消費税初心者のためのインボイス教室 第1回 新たに設立された法人のインボイス発行事業者登録手続き
税理士 佐々木みちよ
【プロフィール】
税理士、佐々木みちよ税理士事務所所長。早稲田大学大学院法学研究科修了。組織再編税制やグループ通算制度、消費税など、企業税務に関するアドバイス業務に従事するほか、税務専門誌への寄稿、税理士及び事業会社経理・税務担当者に対するセミナー講師を行う。
2022年1月から2023年12月まで、税務通信データベースにおいて「消費税初心者のためのインボイス教室」を連載。著書に、『入力業務マニュアル 消費税 経理処理パターン』(共著・税務研究会)等がある。
(2025年9月現在)
はじめに
2023年12月まで連載した「消費税初心者のためのインボイス教室」では、消費税の基本的な用語やインボイス制度の仕組みについて解説し、多くの読者の皆さまからご好評をいただきました。
インボイス制度は2023年10月に導入されましたが、その後も国税庁からインボイス制度に関する新たなQ&Aや、実務に配慮した柔軟な取扱いの具体例が次々と公表され、実務の現場では、今なお制度の理解と運用の定着に向けた模索が続いています。そこで本連載では、こうした最新の動向や実務に役立つ情報をタイムリーに取り上げ、消費税に不慣れな方にも理解できるよう、分かりやすく解説していきます。日々更新される制度運用のポイントを一緒に押さえていきましょう。
| 凡例 |
|
インボイスQ&A
...消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 平成30年6月(令和7年6月改訂) 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
|

1.インボイス発行事業者の登録申請
(1)課税事業者の登録手続き
インボイス発行事業者として登録を受けようとする事業者は、所轄税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します(インボイスQ&A問1)。登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合は登録を行い、登録した旨をその事業者に対して通知することとされています。登録の効力は、通知日ではなく登録日から生じることになり、登録日以降の取引についてインボイスの交付義務を負うことになります(インボイスQ&A問5)。
登録申請書の提出から登録通知を受けるまでに要する期間は、国税庁webサイトで公表されており、登録申請書をe-Taxで提出した場合は約1か月、書面で提出した場合は約1.5か月とされています(令和7年9月1日現在)。
(2)免税事業者の登録手続き
免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者として登録を受ける場合は、登録を希望する日から登録を受けることができる経過措置が設けられています(インボイスQ&A問7)。
この経過措置により登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書に登録希望日を記載します。登録希望日は、登録申請書を提出する日から15日以後の日である必要があります。この場合、税務署長による登録が登録希望日後に完了したとしても、登録希望日に登録を受けたものとみなされ、登録希望日から課税事業者になります。
なお、既に課税事業者である者が登録を受ける場合は、登録申請書に登録希望日を記載することはできません。前述したように、税務署長により登録された日からインボイス発行事業者になります。
【免税事業者が登録希望日から登録を受けるための手続き】

◆参考◆
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためには、本来は、①課税事業者を選択する書類(消費税課税事業者選択届出書)を提出し、②適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する、という2段階の手続きが必要ですが、上記の経過措置(登録希望日から課税事業者になる経過措置)により登録を受ける場合は、①の課税事業者選択届出書の提出は必要ありません(インボイスQ&A問7)。
なお、この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者となることができない点に注意が必要です(インボイスQ&A問7(注)1)。

免税事業者は、登録申請書に登録希望日を記載することで、その登録希望日からインボイス発行事業者になることができます。ただし、登録希望日は登録申請書を提出する日から15日以後の日である必要があります。
2.新たに設立された法人の登録手続き
新たに設立された法人の登録手続きをケース別にまとめると、次の通りです (注) (インボイスQ&A問11)。
(注)課税期間を短縮していないことを前提としています。
(1)設立事業年度の初日からインボイス発行事業者になる
新たに設立された法人は、事業を開始した課税期間中に登録申請書を提出することで、その課税期間の初日(=設立日)に遡ってインボイス発行事業者の登録を受けることができます。この場合は、登録申請書の「事業を開始した課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」欄にチェックを付し、「課税期間の初日」欄に設立日を記載します。


新たに設立された法人は、設立事業年度中に手続きを行えば、設立日に遡ってインボイス発行事業者の登録を受けることができます。
(2)免税事業者が登録希望日からインボイス発行事業者になる
設立事業年度が免税事業者である場合は、登録希望日(登録申請書の提出日から15日以後の日)からインボイス発行事業者になることができます。登録申請書には、その登録希望日を記載します。

なお、設立事業年度の翌事業年度の初日からインボイス発行事業者になろうとする場合には、その初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出します。

(3)課税事業者が登録を受けた日からインボイス発行事業者になる
設立日における資本金が1千万円以上である場合などは納税義務が免除されることはなく、その法人は設立日から課税事業者になります。課税事業者は、登録申請書に登録希望日を記載することはできないため、税務署長により登録された日からインボイス発行事業者になります。

3.登録通知を受けるまでの間の取引
(1)売手の対応
インボイス発行事業者は、登録日からインボイスの交付義務を負いますが、登録通知を受けるまでの間はインボイスを交付することはできません。例えば、新たに設立された法人が設立日に遡って登録を受けた場合、設立日以後の取引についてインボイスの交付義務が生じますが、登録通知を受けるまでの間はインボイスを交付することはできません。その場合のインボイスの交付については、次のような対応が考えられます(インボイスQ&A問37)。
なお、不特定多数の者に対して事業を行っている小売店などは、上記のような個別的な対応は困難です。その場合は、事前にwebサイトや店頭においてインボイスの交付が遅れる旨を掲示した上で、登録通知受領後に、次のような対応を行うことが考えられます(インボイスQ&A問37)。
(2)買手の対応
買手においては、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件になりますが、売手が上記のような事後的な対応を行う場合、登録番号のお知らせ等を受ける前に、買手の消費税の申告期限が到来することも考えられます。
その場合であっても、売手がインボイス発行事業者の登録を受ける旨を事前に確認できているときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除を行って差し支えないこととされています(インボイスQ&A問37)。ただし、後日交付を受けたインボイスや登録番号のお知らせ等の保存が必要になります。

インボイス発行事業者は、登録日からインボイスの交付義務が生じますが、登録通知を受けるまでの間はインボイスを交付することはできません。その場合、売手は買手に対し、事後的に登録番号を知らせるなどの対応が求められます。

本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします